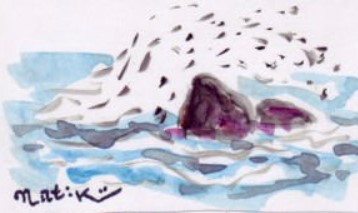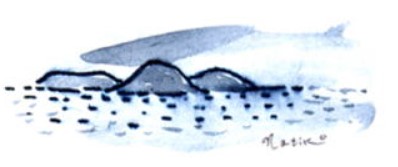18年8月4日 父の俳誌「たこ壷」を語る22
私の十九、二十の頃、元町の為朝公園に象の花子が松林の中の一本の松につながれていた。つながれたまま、右足を一歩前に、それから左足を一歩前にを、毎日その場でくり返していた。前進できないので、前に出した足はまた後に、一歩づつ下る動作をくりかえすのだが、それを見ていると、とても自分も悲しかった。どんな事情で大島で過さねばならなかったのか、ほぼ想像できるが、何とも哀れな月日だった。ところで父の俳句は、これで終わりとなった。はじめた時の楽しさはどこへやら、いざ終わるとなるととても淋しい。この父の発句が終わった頃から「椿の実」を何とかひとつの大島の民芸品にしようという気持が芽生えて来て、発句生活も終わりになったと思われる。父、長島定一の俳句をこうして読めたことと、父のことを新めて見直すことが出来たのはとてもいいことだと思う。いづれ丈雨さんの文章が見つかったら、続篇をご紹介しますが、今回はこれで一旦休憩に入ります。
「むれ燕」「つん潜る」とか、楽しい日本語がたくさん出て来た。日本語の何と楽しいことか。俳句を作る喜びとは、まさにこの言葉の持つ意味や使い方や味わい方を追求してゆく訳で、紙とエンピツさえあれば、とても楽しめる。昔のほうが、こういう生き方、楽しみ方、魂や言語の持つ響きや、深さや色あいを、限りなく学べたのだなアと思う。
晴れた日には伊豆半島の川奈ホテルの窓が朝日に照らされてキラキラと光って見えた。まるで、大島の私達に向って光の信号を送っているようだった。大島が洋上にたった一つポツンと浮かんでいるだけだったら、実に淋しいが、あの川奈ホテルの窓のキラキラ光る朝の風物詩こそ一日の始まる元気の素だった。また、父の出戻りの娘の句を読んだ時から、私は絶対出戻りの娘にはならないと心に誓った。なぜって、私は絶対父を出戻りの娘の父親にしたくなかったからだ。恵まれた結婚生活を無事最後まで全う出来たのも実にこの句のおかげ。大島という素晴らしい故郷に出戻り娘は、一人もいない方がいいに決まっている。
大島の生活は、いくらふんばっても、これ以上はよくならないという、運命的なものがあった。6人の子をかかえ、父の苦悩がしのばれる。せめて、父と子と二人で静寂の麦畠で麦をふむことを夢想したりしたのだろう。長男の伊豆男に旅館を継がせようとしたが、長男は一人で考えを決め、島を出て神学校を受けて牧師となり、島とは全く違う土地に住んだ。父の淋しさが伝わってくる。
どの句を見ても、一句一句が宝石のように尊く思えて来る。あんな質素で素朴でおだやかな時代だったからこそ、人々の行いや息づかいや想いなどが、汚れのない、美しい生活だったのであろう。2句目の句は2女宇受子のことをうたった句、母は病弱だったので、私が母のかわりに妹の入学するのを祝って、ベレー帽と上っぱりを縫って着せてあげた。妹が小さな手で自分の髪をとかす所作を父が見て句にしておいて呉れたことは、何よりも私たち姉妹にとってのプレゼントだと思う。かまどの灰を掻く男とは父の自分の姿をうたったもので、母がいつも寝ていたので、ごはん炊きは父の毎日の仕事だった。 18年7月5日 父の俳誌「たこ壷」を語る17-2
この句会のメンバーで、一番男っぽく情熱的で芯のある人が高村光太郎に似ている丈雨さんでした。句を追及して言葉にも激しさがつのり、歩き方も活発でした。当時のことですから車に乗って来られる人は誰もなく皆さんの自転車で来られる姿が今でも思い出されます。
この句の頃は、昭和30年前後で、大島ガ観光に光を見い出して一生懸命になりだした頃で、それにかかわる私達も生きるために必死でした。私は高校2年で退学し、小さな父の経営する旅館の手助けをすることになりました。ある日、二人のまだ少女っぽい女の子が我が家にお披露目のあいさつに見えました。おリキさんの家の大島の民謡を踊る舞妓さんです。そうして多分一人の年上の方がお力さんの養女になったと思いますが、すべてがはっきりと想い出され、家のこと、自分の青春のことと共に、この句の素晴らしい存在感まで思われてきます。
ここで少年の句が出てきますが、これは兄弟の次男伊豆男、三男経津男、四男紘一、末っ子爽吉のことです。我が家は南洋植物のサボテンや龍舌蘭、君が代蘭があり、手入れのあとの枯葉を捨てるのが大変で、弟たちがその仕事にあたっていました。この句のように、海でじゃれ遊んでいる時が一番楽しかったことでしょう。きびしい父ではありましたが、その姿を見る時は、父の顔にも笑みがあった筈です。
どの句も大島ならではの句で懐かしさに溢れている。大島の自然と暮らしとが、どの句にも必ず感じられ、そしてそれはとても濃い。
大島の楽しみと言えば1月16日の吉谷神社のお祭があった。吉谷さまには小学校5、6年になると、決められた早朝におそうじ当番があり、ふたり、組になって掃除に出かけた。石段を登って境内を清めていると突然半鐘が鳴った。神社と半鐘とはほとんど隣同志だったのでびっくり仰天、寝ぼけているから何ごとが起ったのかと腰をぬかして、石段をころげながら走って家まで逃げた。あの時ほど怖いと思ったことはなかった。ただでさえ人通りのない淋しい道、大きな竹ぼうきをひきずって飛ぶように帰ったが、火事の半鐘は本当に子供にとってはドキッとするものだ。
大島の風物詩は冬の日のあの風の強さと、まるで時間が止まり、何も彼も止まったようなあの不思議な空間の頼りない感覚だ。人は何を思い何を頼り、何のために生きているのだろうと思えて来る。だがしかし、大島全体と自分とは常に一体感があり、父母がいて、兄弟がいて、友達と語り合えて、幸せそのものだった。あの幸せがどんなに極上のものであったか、今にして初めてその値打が解って来る。
暖寒流の遇うところというのは、乳ヶ崎沖の波のぶつかるところを言っている。北の山方面にかけて農耕地が続き、農夫は伊豆半島をのぞみながら畠仕事をする。ある時、昔隔離病院のあった小さな山上に登って伊豆半島を眺めたら、黒潮の波頭がくっきりと、小刀で線をつけたかのように並んでいて、大島の乳ヶ崎沖の潮の早くて素晴らしい様子をみたことがあった。相沢先生発行の「黒潮」のカットに父長島定一の秀逸なカットが何点かあるが、若い時に島に渡って来た時の父の心が、このカットの強烈さの中にかくされてあるような気がしてならない。
我が家の庭に石仏が飾ってあった。それは私と一つ違いの弟がジフテリアで6才の時亡くなった折りに父が伊東の方へ出向いて石屋から買って来て、庭の蘭の葉陰に安置したもの。旅館の庭なのに、それは何となく調和して、まったく違和感がなく庭や建物や私たち8人家族の心と一体感があった。私は毎日8人前食事の用意をしていたが、その弟沙樹男を入れると9人で暮していたことになる。本当に素晴しい島の生活であった。
「たこ壷」のメンバーは白井さん寺田さん、島の新聞社の柳瀬さんら。句会に小田原から招かれて先生がいらした。この折弟の「ツイと啼きて主(あるじ)よろこぶ目白かな」の句が先生に誉められ、弟はそのことで俳句を好きになり、その時の嬉しさはひとしおだったらしく、今でも私に語り、一生の宝にしている、たしか弟はそのころ中学生だったと思う。ちなみに目白は未熟な時は、チーとしか啼かないが、上手になるとツイと啼くようになるのだそうだ。目白を愛する島の生活がほほえましく思える。
大島に住んで旅館をやっている以上、三原山に登る人、宿に泊る人の中には、いろいろと人生航路の問題を抱えている人とたくさん出会う。南島館にも昭和の初期には、自殺しそこなって、そのまま番頭さんや風呂番にやとってもらいたくて居ついた人が何人もいた。昭和も半ばを過ぎてから、父は人命救助に功労があったとして、朝日新聞社から褒賞された。私自身もある時、三原山に登り、火口のふちを歩いていたら、おにぎりの包みとわらぞうりが、きちんと置かれているのを見てギョッとした。そのおにぎりとぞうりは、私が用意したものだったからである。
父の俳句の特徴は、色彩が感じられるし、若々しさがあるので、いつ読んでもすきである。父が俳句をやってくれたおかげで、父の原稿や文字に触れ、句をひねっている時の姿などをみていて、どれほど私たち子供は幸せだったことだろうか。句に関心があるのは私だけかと思っていたら兄弟全員、父の俳句に対して興味を持っていることを知り、驚きと嬉しさを最近味わった。今度ついでがあったら、そのことを宣伝致します。
大島で美しいものはあんこさんと学校の先生です。私の小学校5、6年の時の受持ちは立木政子先生でした。岡田に嫁がれて川島先生になられましたが、美しいペン字で「早春賦」「からたちの花」などステキな愛唱歌を綴って、私にプレゼントしてくださいました。そんな素晴らしいことがあって、私は本当に幸せ者だったと今つくづく思っています。
父は生きてゆくよすがとして俳句を詠んだ。その他に俳友や宗教家、教育者、旅館を営む同業者など沢山訪れてくれる友人がいた。私がブラジルに渡航する際にも、父は「人間は一人では生きてゆけないから、友人は必ずつくること」と助言をしてくれた。
よく学校に通う道すがら、牛の通る姿と出会うことがたびたびあった。それはのどかで豊かで、そして生きていること彩りというものがあって、とてもステキな出来ごとだった。ましてや行き交う山道には真赤な椿の花がそのままの色をして道に落ち、地をうずめつくしていた。ああ、またあのような山道を歩いてみたい。そういえば父はよく湯場へ通っていた。私もお供をして椿咲く小道を目白の声をききながら、よく通ったものだ。その小道や沢づたいに歩いた道は、毎日のように想い出しもするし、夢にも見ている。
父の経営する「南島館」は、小さいながら海辺に建ち、そして南向きのベランダからは三原山が見え、日によっては伊豆諸島も眺められたりして、おあつらえの風流人が泊まるところであった。父は彫刻家だったので、厚い木の台の前に座って旅館をしながら印を彫ったりもしていた。大島に住むきっかけとなったのは、結核を患ったため転地療養したからだった。好きな芸術の道にも進めず、病身の父の心境からして、人生の意義を考えたりする島暮しだったので、俳句を詠むことは誠に父の身の上にぴったりだった。二句目の悔ゆることとは、私と一つ違いの弟(長男)をジフテリアで6才の時に死なせてしまったこと。
世の中にはいろんな人がいますが、帽子を深くかぶって歩いている人がいたりするから面白いです。父は若い頃、街はづれで風景をじっと立って眺めていたら、警官に「おいこら、君は何をしているのかネ」と言われたそうです。時代によってはスパイと間違われたりするのですネ。
一句目は夕陽を三原山から見た時の情景か、もしくは海辺で、利島・新島の方を見た印象を詠んだ句と思われますが、私の大好きな句です。四句目の「饂飩(うどん)煮て・・」は昔の我が家を思い起させる。 |